この節の前後の節へ移動したい場合は下記のリンクから移動できます。
石油産業の歴史 第1章 第6節 国際石油産業の構造変化
このページは、目次![]() 資料編
資料編![]() 石油産業の歴史:第1章 国際石油産業
石油産業の歴史:第1章 国際石油産業![]() 第6節 国際石油産業の構造変化のページです。
第6節 国際石油産業の構造変化のページです。
1. 湾岸危機
1990年8月2日、クウェート侵攻を開始したイラク軍は、瞬く間にクウェート全土を占領した。このため、国連は即日、安全保障理事会(安保理)がイラクのクウェートからの即時撤退を求める国連決議第660号を採択し、対イラク国連制裁を開始した。さらに8月6日にはイラクに対する経済制裁として、「国連加盟国がイラクに対して全面禁輸を行う」国連決議661号も決議した。この間、世界的な油田地帯であるペルシャ湾岸の一部が戦場となったことから、原油価格は急騰した(ドバイ原油のスポット価格が7月の17.1ドル/バレルから9月には37.0ドル/バレルへ2.2倍の高値となった)。しかしイラクは経済制裁が実行されたことでその恩恵にあずかることができなかった。
イラクは、度重なる国連の撤退勧告を無視してその後もクウェート占領を続けたため、11月29日、国連は、1991年1月15日の期限までにクウェートから撤退しない場合にはイラクに対する武力行使を正当化する「対イラク武力行使容認決議案(安保理決議第678号)」を決議するに至った。そして、撤退期限が過ぎてもイラク軍はクウェートを退かなかったため、多国籍軍は1月17日、ついにイラクへの爆撃を開始した(「砂漠の嵐」作戦)。
一方、イラクのフセイン大統領は1月18日からスカッドミサイルでイスラエルを攻撃し、イスラエル最大都市のテルアビブでは死傷者が出た。しかし、多国籍軍による一ヶ月以上にわたる恒常的な爆撃で、イラク南部の軍事施設は壊滅的な打撃を受け、2月27日には多国籍軍がクウェート市を解放、イラク軍は敗走し、米国ブッシュ大統領は同日中に勝利宣言を行った。これを受け、3月3日には停戦協定が締結され、湾岸戦争は終結を見た。
以上が湾岸戦争の大まかな経緯であるが、湾岸戦争の開始時期については、1990年8月2日のイラクによるクウェート侵攻を起点とする場合と、1991年1月17日の多国籍軍によるイラク空爆を起点とする場合がある。いずれにしろ、イラクによるクウェート侵攻、イラクに対する国連経済制裁、湾岸戦争へ発展したこれら一連の騒動を湾岸危機と呼んでいる。
湾岸危機については、日本は原油処理量の拡大、IEA決定(日量250万バレルの備蓄放出を発表)に基づく民間備蓄の取り崩しなどを行い、それまで2回の石油危機の経験が生かされたことから、大きな混乱は起きなかった。このため、湾岸危機はオイルショックには該当しないとする専門家も多い。
2. 米国石油政策の転換
米国は世界有数の産油国であるが、急速な国内需要の伸びに追いつかず、1948年には早くも石油の純輸入国に転じていた。しかし、世界の石油市場は実質的に米国企業を中心とするメジャーズに牛耳られており、実際に問題が生じたこともなかったため、1970年代を迎えるまで、米国にはエネルギー問題を取り扱う連邦政府機関が存在しなかった。
しかし、第一次石油危機の発生は、米国に石油供給の危機を十分に認識させることとなり、カーター政権(1977~1981年)時代の1977年に、米国に連邦エネルギー省(DOE)が創設されることとなった。
米国で国家安全保障の観点からエネルギー政策を策定するようになったのは、ニクソン大統領(1969~1974年)の就任以降である。大統領が就任後に「国家エネルギー政策」を発表する慣わしが生まれたのもニクソン大統領の時である。
1970年代の米国では石油輸入が増加を続け、エネルギー安全保障論議が高まる中で登場したカーター大統領が、1977年4月に打ち出した「国家エネルギー計画」は、国家主導で省エネルギーの促進や新エネルギーの開発などを初めて政策の柱として取り上げたことで注目を浴びた。
これに対し、1981年1月に登場したレーガン大統領(1981~1989年)のエネルギー政策の根幹をなすものは、政府介入と諸規制の排除による「市場原理」の重視である。すなわち、国産原油の価格規制の廃止と高価格の容認により、原油生産の増加、省エネルギーの推進、代替エネルギーの開発、石炭等へのエネルギー転換などを促進しようというもので、法、規制あるいは補助金などによりそれらを実現しようという従来の考え方とは対照的である。
このような方針から、レーガン大統領は、1981年9月までに段階的に撤廃される予定であった国産原油価格の規制注1)を、大統領就任後間もない1981年1月28日に一気に撤廃した。これは、約10年間続いた原油価格規制に終止符を打つものであった。国産原油価格は、これにより直ちに国際価格まで上昇することとなった。
同時に、ガソリンとプロパンに残っていた石油製品の割当・価格規制、中小精製業者に対する原油融通制度である原油のエンタイトルメント・プログラムなども廃止され、米国の石油市場は完全に自由化された。原油価格統制の撤廃が決定して以来、探鉱活動が活発となり、原油の確認埋蔵量、原油生産量の長期低落傾向に歯止めがかかった。
ほかの供給拡大策としては、石油・天然ガス資源の賦存が予想されている連邦所有地、特に外縁大陸棚(Outer Continental Shelf)の開放が促進された。エネルギー安全保障関係では、石油の戦略備蓄(当時の目標は1993年までに7億5,000万バレル)の強化が行われた。
レーガン大統領の後に誕生したブッシュ大統領(1989~1993年)は、「市場原理」重視の方針を継承し、石油輸入依存度の軽減と電力市場自由化を骨子とする「エネルギー政策法」を議会で可決させている(1992年)。
その後誕生したクリントン政権(1993~2001年)は、エネルギー政策の基本スタンスとしては、実質的に「市場原理」を踏襲しているが、1998年4月に「包括的国家エネルギー戦略」を発表した。これは地球規模で議論が沸き起こっている気候変動問題を背景に、政府が再生エネルギーの利用を推進しようとする初めてのエネルギー政策であった。また、1999年4月に、クリントン大統領は「政府グリーン化のための計画」を発令した。これは、米国最大のエネルギー消費者である連邦政府に対し、国庫の節約のためだけでなく、大気汚染と地球温暖化への対応も目的として、大気汚染物質の排出抑制を命じたものであった。このように、クリントン大統領のエネルギー政策には、省エネ推進、再生可能エネルギーの技術開発促進、環境保護重視など民主党のカラーが強く打ち出されたのが特徴であった。
3. メジャーの変貌
第二次石油危機(1978年10月~1982年4月)で、革命後のイラン新政権が消費国との直接取引やスポット販売を拡大し、メジャーズを経由しない石油の販売が増加してメジャーズの影響力低下が決定的となっていた。
また、アジア経済危機(1997年7月のアジア各国の通貨価値の下落に端を発する金融・経済危機)の拡大による世界の石油需要低迷などから、供給過剰となった原油の価格は低迷し、ドバイ原油の1999年2月平均価格は10.02ドル/バレルまで下落し、1986年の価格暴落以来12年ぶりの安値となった。
こうした状況に危機感を募らせたメジャーズは石油会社の再編に乗り出し、その動きは原油価格が大幅に下落した1998年から活発化しており、BPが1998年8月にアモコの買収を発表し、社名も「BPアモコ」にすることを決定した。
1999年11月に売上高世界第1位で上場石油会社としては世界最大の米国エクソンと売上高米国第2位のモービルが、2000年4月には売上高世界第3位のBPアモコとアルコが、そして2001年10月にはシェブロンとテキサコがそれぞれ合併し、「エクソンモービル」、「BPアモコ(現在のBP)」、「シェブロンテキサコ(現在のシェブロン)」が発足するなど、合併・統合の嵐が吹き荒れた。
その結果、1970年代初めまで世界の石油市場を支配し、セブンシスターズと呼ばれていた7大メジャーズが、「エクソンモービル」、「ロイヤルダッチシェル」、「BP」、「シェブロン」の4グループに集約される結果となった。
こうした大型合併・統合は、コスト削減などによる経営合理化、規模を拡大することによる財務体質の強化、株価の維持・向上を図ろうとするものであり、原油価格の大幅低下による経営悪化に対するメジャーズの対抗措置であった。
もともと歴史的に見れば、エクソンもモービルも、スタンダード石油(ロックフェラーが1870年1月10日にスタンダード石油・オハイオを創設したことに始まる)が1911年に連邦最高裁判所からシャーマン反トラスト法違反で分割命令を受け、33社(34社とする説もあり)に分割された際に誕生した会社である。
そしてスタンダード石油が分割させられたのは、同社が1900年代初めまでに、米国の販売シェアの80%、製油能力の75%、ほとんど全てのパイプライン、原油生産の40%をおさえ、価格支配者になりうる大きなシェアを持つ会社に成長していたためであった。したがって、エクソンとモービルが合併するということは、スタンダード石油が復活することであり、一昔前なら到底考えられなかった事態である。
4. 先物市場の台頭
これまでの歴史を辿ってみると、国際原油価格の歴史的な転換点としては以下の4回を数えることが出来る。
1回目は第一次石油危機(1973年10月~1974年8月)の時で、このときに価格決定権がメジャーズから産油国に移った。
2回目は第二次石油危機(1978年10月~1982年4月)の時で、このときはメジャーズの価格決定への影響力低下が決定的になった時期ということができる。
3回目は1986年の原油価格下落の時期で、原油価格は一時10ドル/バレルを割り込む事態となった。これは世界的に石油需要が減少した中で、それまで価格維持のために単独でもスイングプロデューサーとして生産調整を行ってきたサウジアラビアが、その役割を放棄し、増産したことで原油価格の暴落を招いたものである。これは、基準価格制が崩壊した時期ということが出来る。
そして、4回目は1990年代後半以降の先物市場価格台頭の時期である。この4回目の転換点の時期を特定することは難しいが、1990年の湾岸戦争後に現れ、1990年代後半以降に確実となった変化である。即ち、現物のスポット市場価格ではなく、先物市場価格、特にアメリカのNYMEX(ニューヨーク・マーカンタイル取引所)に上場されているWTI(ウエスト・テキサス・インターメディエイト)の先物価格が、世界の原油価格決定に大きな影響力を与えるようになった。
第二次石油危機以降、メジャーズによる原油支配体制の崩壊と市場の多様化は、国際的な原油取引を仲介する原油トレーダーの活躍の場を広げ、需給緩和と価格の不安定化は、原油を一般の国際商品のように市況商品化させる傾向を強めた。こうした動きを受け、1983年には、ロンドンとニューヨークの先物市場に原油が登場し、原油の先物取引は、国際市場における先行指標としても次第に重要な意味をもつようになった。
WTIは1983年、ニューヨークの先物市場であるNYMEXに上場された。取引は順調に拡大し、2016年にはWTI先物取引の規模は1日当たり約11億バレルと、世界の原油総生産量(1日当たり約9,700万バレル)の11倍強にも達している。
なぜこうした現象が起きているのか。それはヘッジファンドやコモデティーファンドと呼ばれる投機筋が市場に介入しているからである。こうした人々は、株価や為替動向などを睨み、石油先物が良い商品であると判断すれば原油先物市場に参入してくる。投機筋として石油先物市場を利用する人々は、「実際に現物としての石油を買いたい」わけではなく、価格が高騰すれば先物予約権を売却し、利益を確保するということを目指す。
このため、先物市場の価格動向は、需給関係のファンダメンタルな要因でも値動きするが、地政学的なあるいは資源ナショナリズムに関係するニュース報道などにも敏感に反応して大量の「買い」が入ったり、逆に「売り」が発生したりする。その結果、先物市場の原油価格は、甚だしい高値を付けるという事態を発生させる危険性もある一方で、スパイラルな価格下落を引き起こす可能性もある。このため、1990年代後半以降は原油価格乱高下の時代と呼ぶことが出来る。
- 図 1-6-1 原油価格の推移(月平均)
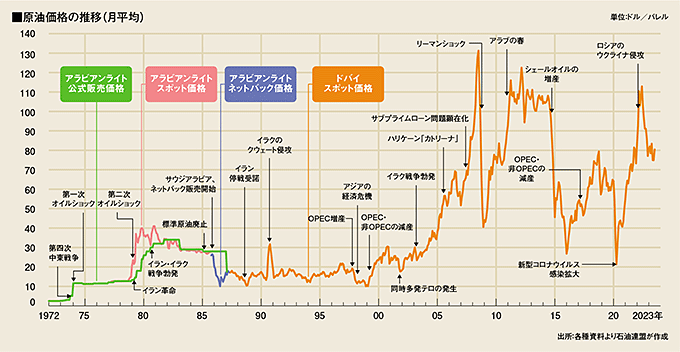 出所:石油連盟「今日の石油産業2023」
出所:石油連盟「今日の石油産業2023」
- [注]
- 注1)1973年11月に制定された緊急石油配分法に基づき、国産原油を対象に実施された。同一生産施設から生産される原油の量が、1972年の同月の生産水準以下の場合は、その全量を旧原油(オールドオイル)とし、その価格を1973年5月15日の公示価格+1.35ドル/バレルに固定し、生産水準を上回った場合は、超過部分を新原油(ニューオイル)として価格統制を行わない、という内容であった。
この節の前後の節へ移動したい場合は下記のリンクから移動できます。